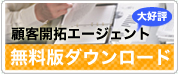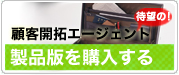‘営業用語集’ カテゴリーのアーカイブ
アウトソーシングとは
2009 年 7 月 8 日 水曜日委託販売とは
2009 年 7 月 8 日 水曜日委託販売(いたくはんばい)とは、企業がとる販売活動形態の一種である。また、個人でも、同人活動、個人販売などにおいて企業又は個人に依存して委託販売を行うこともあるが、この場合は、厳密な会計処理が行われないことも多い。
サードパーティー・ロジスティクスとは
2009 年 7 月 8 日 水曜日本項では物流業務を委託する側の企業を「荷主企業」、委託される側の企業を「3PL事業者」と表現する。なお、3PL事業は許認可制でないため法的には3PL事業者なるものは存在しない。ここでは「3PL事業の展開を公称する企業」をもって3PL事業者の定義とする。
サードパーティーとは
2009 年 7 月 8 日 水曜日サードパーティー(Third party)とは、直訳すれば第三者的な目的のある集団・団体を指すが、特にコンピュータ関連の用語では、コンピュータ本体を製造するメーカーとは、直接の関係がないメーカーを指す。またはそれらから提供される製品を指してサードパーティー製品(非純正品)と呼ぶ。反対語としては純正品がある。主にハードウェアに関してこのように表現するが、一部ソフトウェア製品に関しても、このように呼ぶ場合がある。
本項では主に、コンピュータ関連用語に関して述べる。それ以外の同語に関しては語義(下記記事)参照の上、各々の項を参照されるか、別の呼び方を参照のこと。
ステークホルダー 利害関係者とは
2009 年 7 月 8 日 水曜日説明責任とは
2009 年 7 月 8 日 水曜日説明責任(せつめいせきにん、アカウンタビリティー(Accountability) の日本語訳)とは、政府・企業・団体などの社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株主や従業員(従業者)といった直接的関係をもつ者だけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的関わりをもつすべての人・組織(ステークホルダー:stakeholder、利害関係者)にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。
企業の社会的責任 CSRとは
2009 年 7 月 8 日 水曜日企業の社会的責任(きぎょうのしゃかいてきせきにん / 英記:CSR: Corporate Social Responsibility)は、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー (利害関係者:消費者、投資家等、及び社会全体) からの要求に対して適切な意思決定をすることを指す。
企業の経済活動には利害関係者に対して説明責任があり、説明できなければ社会的容認が得られず、信頼のない企業は持続できないとされる。持続可能な社会を目指すためには、企業の意思決定を判断する利害関係者側である消費者の社会的責任(CSR: Consumer Social Responsibility)、市民の社会的責任(CSR: Citizen Social Responsibility)が必要不可欠となるといわれる。
国際標準化機構 (ISO) では、対象が企業(Corporate)に限らないという見地から、社会的責任(SR: Social Responsibility)の呼称で国際規格の策定作業が続けられている。
簿記とは
2009 年 7 月 8 日 水曜日簿記(ぼき)とは、ある経済主体が経済取引によりもたらされる資産・負債・純資産の増減を管理し、併せて一定期間内の収益及び費用を記録するための記帳方式である。また、最も一般的な簿記である複式の商業簿記を指して単に簿記と称する場合が多い。会計学よりも実務に近い部分のことをいう。
ドミナント政策とは
2009 年 7 月 8 日 水曜日ドミナント政策(dominant strategy?)とは主にチェーン展開している店舗の出店施策の一つでビジネス用語。ドミナント出店、エリア・ドミナンス戦略とも言う。時に出店そのものを指すことがある。dominant の元来の意味は優位・支配。
日本であれば47都道府県や市町村全てを対象にした絨毯爆撃のような出店を行なわず、特定の地域の例えば関東地方であれば東京都・埼玉県・神奈川県などの一都二県等の限定した地域を対象とした集中的な出店や特定路線沿いに次々と出店し同一商圏内の競業他社や競合他店に比べて市場シェア率の向上獲得や独占を意図した出店戦略や出店計画を言う。
ハイパーマーケットとは
2009 年 7 月 8 日 水曜日ハイパーマーケットでは総合食品・日用品を中心に据え、その他に衣料、DIY用品、書籍、玩具などを含めた多岐にわたる商品を倉庫をそのまま店舗として使用しているような大きなスペースに陳列する。顧客は購入希望の商品を用意されているショッピングカートに乗せて集め、出口ゲートを兼ねたレジにおいて決済手続きをする。専門の売り場ごとに決済をするゼネラルマーチャンダイズストアとはこの点が大きく異なる部分である。
この形態は典型的な郊外型の店舗であり、屋上または周囲に大規模な駐車場を設けてあり、まとめ買いをする顧客をターゲットにしている。建物の外装には余りコストをかけず天井がむき出し(配管などが見える状態)であることが多く、ショッピングカートで移動しやすいことに着眼点のある売り場設計がなされていて、1階から多くても3階建ての建物で各フロアの面積が広い。加えてエスカレータはショッピングカートをそのまま乗せることができる斜度が低くステップが段差にならないものが使用される。
大量仕入れをすることや店舗外装にコストをかけないようにしているため、スーパーマーケットなど他の形態の店舗の販売価格よりは商品が2割~3割安く売られている場合が多い。世界に先駆けカルフールがハイパーマーケット形態の店舗を出店したことでよく知られている。